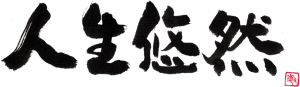2019年の年末になって秋元国会議員が逮捕された。彼はカジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業法案を成立の中心人物でした。容疑は日本参入を目指していた中国企業からの収賄容疑であった。3年前にIR整備推進法が成立するとすぐに中国企業が日本法人を設立して、接触を図り、積極的なアプローチをしていたようです。
権力を持った途端に、甘い蜜に蟻などの昆虫が集まるように特選的利益を得ようとする人々が群がります。また、特権を持った人は、自分の実力であると増上慢になり、その特権を行使することができると錯覚して、よほどの自制心がないと知らぬ間に足を捕られることになります。
少し前の事例ですが、3年前に東京都の舛添知事がこの罠に落ちて辞職を余儀なくされました。
なぜそこまで追求されたか。
3年前に「生きるとは何か」(58)に書いた文章から一部引用します。
2016年6月20日に舛添東京都知事が辞職しました。あれだけ騒いだTV、新聞などのマスコミや都議会議員も、昨日までの暴風雨が過ぎ去り、青空を見上げるような安堵の姿をみると、臭いものに蓋をした、これで終わりだと言わんばかりの変わり身の早さにはいささか驚きます。後味の悪さを感じますので、問題の本質は何か、を考えてみました。
元はと言えば、都知事が高額な海外出張費を遣い、どこかの王族のような豪遊視察や、毎週末の公用車を使った湯河原別荘通いを指摘されたのが始まりです。世界的な大都市である東京の都知事に相応しい振る舞いをしたのであり、公用車での別荘通いは動く知事室であるなどと強気の言い訳をしていました。しかし、週刊誌上で都知事になる前の政治資金のケチな使い方(家族旅行、絵画、書籍の購入など)が報道されてから、私たち庶民から見てもあまりにも“せこい”公私混同の金銭感覚に愛想が尽きて、庶民パワーに押され都議会も不信任案を出さざるを得なくなったのが実情でしょう。最近の新聞によると、都幹部の話として、知事は金曜の午後2,3時台に出発するケースが多く、週末は別荘で過ごす。都のルール的には公務後の「帰宅」扱いであるが、舛添氏は「別荘からの帰り道は事務所の車を使っている」などと弁明し、「ルール通りで問題ない」と主張していたとのこと。人事権のある知事には、それ以上強く言えなかったと幹部は悔やんでいたようです。エリート秀才の中身
一般常識からすると、舛添氏は東大法学部でトップを争うほどの秀才で、政治家に転身して厚生労働大臣も歴任するほどの凄腕の人物と評価されていました。しかし、私生活では複雑な家庭事情を抱えて表の顔と裏の顔はかなり異なり、傲慢でエリート意識が強く、名誉欲があり、自己中心的な性格と思われます。多分、法律や経済の知識は豊富にあり、世間的な処世力が優れていても、残念ながら人間としての質(人格)はかなり低く、心の成長が見られなかったために、人生の絶頂期に奈落の底に墜落したのでしょう。例えれば、自分の蒔いた種が成長して、ウドの大木となり、強風で脆くも倒壊したようなものです。今回のごたごた劇で、強い挫折感を感じている(?)ならこの機会に、深く自分の行動を顧みて、避けることができない因果法則(善因善果、悪因悪果)に沿っての結果であることを認識できたら再生も可能ですがどうでしようか?
ここまで書いてから最近の舛添氏の活動をインターネットで調べて見ました。そこには1年後に出版した著作、題名は「都知事失格」、自身の反省と後悔の弁が語られていました。試し読みの欄があり開いてみると第一章「誰が私を刺したのか」でした。まえがきは全文あり、私の政治の原点は母の介護である。しかし、介護のことで地元の行政と対立して、さらには兄弟姉妹間で骨肉の争いが続いている故郷では仕事がやりにくいので、自分の住んでいる東京で首長に挑戦したとありました。

この方は、世間で言う秀才であり、行政能力があり、理屈では人を遣り込める弁舌もあるが、人徳のない人で、人格は失格と思います。やはり心を育てる機会(縁)もなくエリートとして邁進し、民衆を愚民と見くびった結果が都知事失格であったのでしょう。本の感想・レビュー欄には彼の強弁に対して否定的な意見の方が多く寄せられています。
充実した時間を生きる
定年後の人生を余生と言って、余った時間であると考えるのは人生100年時代などと言われている長寿社会では間違いであると思います。人にもよりますが20年30年とフリーな時間があるのです。人生の仕上げに向かった非常に大事な時期ではないでしょうか。 がむしゃらに仕事に向き合ってきた前半は世間の中で多くの経験と貢献をしてきたはずです。その経験を生かしながら、どのようにしたら社会に還元できるか、人それぞれの向き合い方があると思います。しかし、前半の人生の経験がすべてであると思い込み、それに固執すると後半の人生には障害となります。舛添氏の前半はあまりにも個性が強く、専門の学問に自信があるので、その殻を破ることは到底出来そうもありません。
2016年当時のもので、彼の心の中を覗くことのできる東洋経済オンライン記事『日本人が信じてやまない「法治主義」の死角』という記事をみますと、それが心の岩盤になっていると感じます。
舛添前都知事の心を覗く
8月に入り新しい女性都知事が誕生しましたが、失職した舛添前都知事の心の闇に切り込む記事を目にしたので紹介します。東洋経済オンラインに中島義道氏の「日本人が信じてやまない「法治主義」の死角 」「舛添問題は哲学的に見てきわめて興味深い」と題名の付いた記事(2016年7月29日)の中で、
・じつは、私は舛添さんとは3年間、職場を共にしていた。1984年3月に4年半滞在したウィーンから帰国し(私はすでに37歳でした)、東大駒場の「社会科学科」のうち「社会思想史」の助手になったのですが、そこに2歳年下の舛添さんがいました。 当時、彼は新進気鋭の助教授。助教授と助手とのあいだには身分上の太い線が引かれていて(助教授はよほどの不祥事を起こさない限り定年まで東大に在職できるけれど、助手は3年経ったらほかの大学に「とばされる」)、対等にはつきあえる間柄ではなかった。まあ、「国際政治」という彼の専門に私はまったく無関心であり、とくに話す内容もないので、つきあうつもりもなかったのですが。
・廊下で会うと軽く会釈する程度であり、東大法学部の首席を鳩山邦夫さんと競い合った超秀才の舛添さんにとって、うろうろ迷い続けた末、やっと37歳で助手にたどり着いた私など眼中になかったのでしょう。 ただ、社会科学科では、先生方は書物を刊行するとすべての同僚にそれを献本する習慣がありましたので、舛添さんから著作が献本されるや否や読み、ほかの助手仲間と一緒にさかんに「誉めた」思い出は何度かあります。
以上は著者と舛添氏との関係、舛添氏の超秀才ぶりを示す部分からの引用ですが、ここからが本論です。
・舛添さんが公費を私的なことに流用しているという疑惑が出たとき(「湯河原通い」あたりから)、当時の彼の応対ぶりを見れば一目瞭然ですが、そこにはまったく何の問題もない、と確信していたようです。「第三者」である彼が選んだ2人の弁護士による調査報告のあたりまでは、舛添さんは何を追及されても「お前ら、法律や行政を知らないな」と言いたげな、人を食った素振りでした。彼は法律や政治の第一級の専門家であり、大臣まで務めた経験豊かな政治家でもあって、まさに「俺は裏の裏まで政治の世界を知っている、素人やザコは黙れ」という、高をくくったような態度でしたねえ。私は、こういう現実感覚は嫌いではなく、むしろ「そうであるな」と評価するところです。舛添さんの神妙な表情のすぐ裏から、「俺のような何でも知っている専門家を、薄っぺらな正義感とか甘ったるい庶民感覚を持ち出して批判するとは、ちゃんちゃらおかしい」という思いが、テレビ画面を通じてビンビン伝わってきました。
・たぶん舛添さんは、あの時点でいずれ事態は収束すると考えていたのでしょう。政治の現場はそんな「せこい」批判が通用するところではない、と信じていたのでしょう。公金の私的流用に関する弁護士の「不適切でも、違法ではない」という要約を聞いて、舛添さんは「みなさん、おわかりか? 本当の法律専門家の判断とはこういうものなのだ。これほどまでに俺は誠実に対処したのだよ」という思いさえあったような気がします。
・そして、まさにここから、舛添さん自身思いもよらない方向にメラメラと「不満」は燃え上がり……気がついてみたら手がつけられない状態に至ってしまった。私的流用の一部を返金すると言っても、知事の給与を削減すると提案しても、せめてリオ五輪まで待ってくれと訴えても、すべて聞き入れられなかった。即刻辞職しか、残されていなかったのです。
・この流れは、哲学的に見てきわめて興味深いものがあります。舛添さんが事態を収拾しようと「違法ではない」という公式見解を得たのに、その口先だけのきれいごと、ひどいごまかしに、みな腹が立った。舛添さんの「常識」はガラガラ崩れていったのです。納得しない若者の肩を抱いて「世間とはそういうものだよ」とじゅんじゅんとお説教する「大人」のうす汚さにそれまで従っていた若者が、がぜん反旗を翻したのです。
・私も法学部の「刑法総論」の最初に、同分野の権威である平野龍一先生から「100人の真犯人を逃しても、1人の冤罪を防げればいい」という近代刑法の理想を学びました。被告人Aに自白しか証拠がない場合、あらゆる状況から考えてAが真犯人らしいとしても、「法律上は」有罪としない、というだけのことであり、裁判所はこれによって「絶対的真実」を宣言しているわけではありません。
カント的に言えば、法律は真実より重要なものを守っているのであり、それは人権であり、公平であり、法的安定性です。これこそリーガルマインドであって、法学部での秀才たちはこの精神を学んで、行政に司法に、そして立法にも散らばっていく。というわけで、東大法学部出の秀才だからこそ、舛添さんは法に真実を求める「初歩的ミス」を犯す素人たちがおかしくてならなかったのでしょう。「不適切だが、違法ではない」というお墨付きにより、一件落着、あとはいくらでも誠意を示し頭を下げて回れば、知事の職は安泰だと高を括っていたのでしょう。それが崩れたのですから、今回の事件はなかなか哲学的に考察の価値があるということです。
・再確認しておくと、私はとくに舛添さんを批判するつもりはない。そして彼は、――あえて比較をすれば、フランス革命のときにパンがないと騒いでいる庶民の気持ちがまったくわからなかったマリー・アントワネットのように、――いまなお、なぜこういうことになったのかよくわからないのではないかと思われる。 もちろん、私は、この事件に対するジャーナリズムや「一般庶民」の態度や発言に対して、いささかも肩を持とうとは思わず、むしろそこにも舛添さんに引けを取らないほど非哲学的なうす汚れた空気が漂っている、と言いたい。
私がこの文を引用したのは、著者と少し異なる観点で注目したからです。舛添氏のような秀才だからこそ今回の不祥事を引き起こすのではと考えました。法学部は当然ながら法律や行政を学ぶところです。しかし、法律は社会の秩序をつくり、維持するために人間が作った約束事で、自然の真理などではないのです。彼の心の中では、「自分のしたことは不適切だが、法律的には違法ではない、お前らは法律や行政を知らない素人やザコだ、黙っていればいいのだ」との態度が見えたと、身近にいた元同僚が語っています。私などは、あれだけ執拗な追跡や批判を浴びせられても平然としていたのを見て、どのような気持ちなのか心の中を推し量ることはできませんでした。しかし、その道の専門は、都議会内でのやり取りや態度から彼の心の中の言葉が読み取れたのでしょう。専門家で、優秀であればあるほど、法律がすべてで、それに従ってすることが善なる行為になると信じて疑わない信念になっています。例は悪いですが、新興宗教に洗脳された人たちとある意味では同じです。
心を育てる方法
人間にとって、心を育てることは最も重要なことであるが、心を育てるといっても、本人が自分の心は汚れ(欲望、傲慢、名誉欲、詭弁、執着、怒り、物惜しみなど)があると気づいていなければ手の打ちようがない。仏教に「縁なき衆生は度し難し」という言葉もあります。
テーラワーダ仏教のスマナサーラ長老は著書 A・スマナサーラ、鈴木一生『上座仏教 悟りながら生きる』(2006年、大法輪閣)の中で、
「心は自らをきれいにすることを嫌っているし、落ち着かせることも嫌う。ただ混乱状態のままに欲望と嘘の塊のままで生きていたいという習性を持つ。心は、放っておけばいつまでも汚れたままで決してきれいになろうとはしないから、その結果として自分の悩みや苦しみはいつまでたっても消えないことになる。」さらに、「嘘やお世辞など、真実から遠く離れた世界こそ心の最も好む場所である」とも述べています。
このような心の癖を持った人間が、汚れを落として清い心になる方法はどうすればよいか、スマナサーラ長老の著書の力を借りてまとめてみました。
百人の人間がいれば百通りの道がある
・人間は自分の人生経験のなかで、心をある程度成長させることができることも事実である。心理学をはじめ人間を扱った書物を勉強することでも心は育つだろうし、どこか旅に出てさまざまな現象に遭遇することからも、心を成長させることは可能である。あるいは、大きな不幸に見舞われて、その辛苦に立ち向かい、それを乗り越えることによって、心を成長させることもあるだろう。とういことは、心を成長させる機会はどこにでもあるし、どんな方法でも心を成長させることは可能なのである。要は、自分の考え方ひとつなのである。
・心の完成を目指して、どんなにそれが尊い教えであっても、それを聞いて体験した人間の心になんの影響も及ぼさなければ、その教えはその人にとっては、それこそ馬の耳に念仏となってしまいます。
・お釈迦さまはその目的のための方法手段は問わないが、「実践するに当たってひとつのことにこだわれ」と言われる。それは、「その修行によって自分が、執着や怒りの心がなくなり、心が清らかになっているかどうか」ということだけは常にチェックすることである。
全ての人間は、生まれも、生きる環境も、そこでの経験も異なり、考え方も違うのです。それゆえに、心を育てる方法や手段はこれしかないと拘らずに、種々な経験を乗り越えるなかで、心の完成を目指しなさいと釈尊は説いているとのことです。
いいことをする勇気を育てる
・人間の心には、「だまって放っておけばどこまでも汚れていく」という法則がある。心を何もしないで自然のままに放っておけば、必ず悪く穢れた方向へと行く仕組みになっている。と言うと、たいていの人たちは「本来、心と言うものは清らかで、穢れのないもの」と思い込んでいるので、「そんなバカな」といぶかしげな顔をこちらに向けるのである。しかし、残念ながら、心は例外なく、放っておけば墜落してとんでもない方向に行ってしまう本能がある。・分かりやすい卑近な例では、我々は子供のころ自分から進んで勉強したしたという記憶があるだろうか。勉強がイヤイヤで、お母さんからガミガミ言われさえしなければ、勉強など放ったらかしていつまでも外で遊んでいたかったのではないだろうか。子供に自分勝手に生きなさいと言えば、言われた子供は前後の見境もなく、心の赴くままに育っていくことになる。自分の心をコントロールすることもできず、自分を律することも知らない。その結果、どんな人間になるかは自明の理である。こころは、こうした規制をしなければ大変危険な方向へと向かってしまうのである。
・人間は、いい行為をしにくいものである。電車のなかで老人に席を譲る行動ひとつを取ってもみても、なんとなくそうした行いはしにくいと思っている。その逆で、悪いことや快楽を求めるときは、なんの逡巡もなくすぐに行動に移してしまう。この場合の悪いことと言うのは、法律を犯したりすることでなく、勉強しなくてはならないのにそれをサボったり、怠けたりする行為を指す。
いいことをするには勇気が必要です。電車で老人や障害のある人に席を譲るにしても、少しの勇気がいるのは体験することです。小さな善いことが普通にできるようになれば、それだけ心は清くなっています。
一日に一度は自分の心と向かい合ってみる
・心はただただ、今この瞬間の刺激を求めようとする。いいことであろうと悪いことであろうと。そんなことはお構いなしに、すぐ目先の現象を追いかけて行く。自分にとって、それがいい結果になるか、悪い結果になるかという判断すらも心にはできない。善悪の区別がつかないところは、幼児と全く同じである。
・この状態を、仏教では無明と言う。無明とは、明かりがない状態、心がさえていない状態、智慧のない状態をいうのである。無明とは、人間が欲望という催眠術にかかっているときの状態であり、そのために目の前の真理を見ることができない。心は、まさに無明そのものである。・人間の心の働きは、何かものを見たらなにかをしたくなる。何か音を聞いたら何かをしたくなるというものである。匂いを嗅いたら、口で味わったら、何かに触れたら、心は何かをしたくなる。この、心の働きを促すエネルギーを「行」と言う。このエネルギーが自分の中に生じると、行動を起こす原動力となり「何かをしたい」という気持ちになっていく。
・イヤな感情も好ましく思う感情も、それがそのとき別にアクションを起こさなくても、心にしっかりと記憶されていく。この記憶される働きを仏教では、「業」と言うのである。ということは、「行=業」ということでもある。私たちは、眼で何かを見ればそこで「業」をつくり、耳で何かを聞けば「業」をつくっていく。
・人間はこの「行=業」によって、「生きていきたい」というエネルギーを作り続けているのである。何のために人は生きているのか、そんなことは誰も知らない。それは、人間が理由も分からずに、ただ生きたいというエネルギーだけで生きているからに他ならない。その理由もわからない働きが「行=業」である。この生の仕組みからは、誰も逃れることができない。
人間は五感を通して、瞬間、瞬間に業をつくり生きているので、怒りや喜び、好き嫌いなどの感情が生じているのです。この生の仕組みは、誰も逃れることができないとしても、この事実を知っていることで、ついやってしまう自分の愚行に気づくことができます。静かに坐り、一日の行動を顧みて、自分の心と向かい合ってみるのは意義あることです。
何があっても心はクールに
・人間が生きているということは、皮肉にも常に心を汚していることだといえるかもしれない。しかし、心の仕組みのメカニズムを理解すれば、それは納得いくことであろう。どんな人間でも、何か見たり聞いたりしたときに、知らず知らずのうちに小さな感情をつくっている。日常生活のなかでは、強い感情を湧きたたせるような衝撃的なできごとはそうそうないだろうから、その感情は感情と呼べぬほどのものかもしれない。しかし心は、何かものを見た一刹那に、プラスかマイナスか、あるいは無関心か判断をしているのである。
・その自覚できないような小さな感情が大きくなったものが、怒りや欲望というかたちになって現れる感情である。我々の毎日を見れば、怒りや欲望とはっきりとわかる病的とも言える世界で生きているのであるから、心は穢れの真っ只中で棲息しているようなものである。
・この悪業ともいえる心の働きにストップをかけ、心のなかをきれいにしてしまう修行の方法が、仏教の瞑想法である。この心を成長させる方法にはふた通りの道がある。
一つがサマタ瞑想であり、もう一つがヴィバッサナー瞑想である。
・サマタという言葉の意味は、落ち着く、クールになる、冷静になるということである。サマタは、心を何かにひとつのものに統一し、そのことに集中させることによって冷静さを引き出す方法である。
心が統一されると、人間はとてつもなく気持ちがよくなってくる。統一のレベルの程度もあるが、かなり深く集中して統一できた段階であれば、たとえば、人間の愉悦という状態がどんなものであるかを味わうことができる。この喜悦感を味わうとき、人間は欲望から離れることが可能となる。
私たちの日常は、「心の穢れの真っ只中で棲息している」と言われるがまさに、TVや新聞の記事を見ていると悪事や愚行のオンパレードで、欲望と怒りの渦巻く世界であると実感できると思います。クールになれれば真実が見えて、怒りや欲望から離れることが可能であるとの教えです。
すべてのできごとは想念の結果
・サマタ瞑想は、「やればやるだけ喜びは増える」というシステムになっている。瞑想の深さを四つ段階(第一禅定から第四禅定まで)に分けて説明している。(ここでは紙面の都合で詳細を省略します)サマタ瞑想でお勧めしたいのは、「してもらう」ではなくて自分からしてみる「慈悲の瞑想」である。慈悲の瞑想はまず自分の幸せを念ずるところからはじまる。
「私は幸せでありますように」
「私の親しい人は幸せでありますように」
「生きとし生けるものは幸せでありますように」というように、自分や親しい人、さらにはこの世のすべての生命に対して、その幸福と悟りを願って真剣に念ずるだけの瞑想だが、念ずるだけで心のなかに慈しみのエネルギーがどんどん湧く。自分だけでなく他人やすべての生命の幸せを願うことによって、そのエネルギーはさらに強く育っていくのである。これだけでサマタ瞑想の第二段階の禅定まで進むことができる。
・慈悲の瞑想は、正直に、真剣にただ心に念ずるだけなのだが、念じていくと必ず結果が出てくる。それは、この世のすべての現象は、ことごとく心の作用によって結果が出てくるからである。この世のすべてのできごとは、我々一人一人のこころの想念の結果であり、心が影響しあって作られている。
心がきれいになれば、人やすべての生命から慕われ、その結果幸福感が増し、反対に心が汚れれば周りの人から疎んじられ、人間関係もうまくいかず、自分の身体も穢れ、病気になったり、苦しみが増えたりする仕組みになっている。一人怒りっぽい人がいれば、その人が会社に行けば周りの人と喧嘩ばかりしてみんなが不愉快になるし、家に帰ってくればその瞬間から家族全員が怖がって、気分が悪くなる。これは、みんな心の影響である。心の発する波動は、かくも影響力が強く、すごい力を持っている。
私たちは、はっきりと目に見える身体と心を持っているが、心は匂いもなく、形もなく捉えどころのないものです。この肉体と心は切り離すことのできない「心身不二」な関係にあります。身体については、常に気を付けて健康管理をし、衰えを少しでも遅らせるために、運動をして、サプリメントを飲んで、紫外線にあたらないように、美しくありたいと化粧をし、あらゆる手段を講じています。しかし、心の仕組みや、心の成長にはほとんど関心が持たれていなのが実状です。健康にも、人間関係にも大きな影響を与える心について強い関心を向けたいものです。
瞑想法で育つ心
・ともすれば、人間はいつも自分の幸せだけを考えて生きてしまう。自分勝手で自分さえ良ければそれでいいと考えてしまうのが、人間の悲しき性である。そういうふうに生きていると、必ずトラブルが持ち上がる。この「自分さえ良ければ」と思って生きているところに、苦しみを生む萌芽があるのだ。
「自分さえよければ」と考えていても、世の中は自分の思いどうりにはいかないからである。心のなかに苦しみや悩みが芽生えてしまう。
自分中心主義を捨て、すべての生命が幸せであることを願うとき、人間ははじめて慈しみのエネルギーをつくることができ、そこに苦しみのないほんとうの幸せを生み出すことができるのだ。
「慈悲の瞑想」を実践したその日から幸せを得ることができるというのが、この世の真理なのである。断わっておくが、「慈悲の瞑想」は儀式ではない。あくまでも単純な科学なのである。真理なのである。
・サマタ瞑想法というのは心を落ち着かせることが目的である。心は落ちついてさえいれば、怒りも嫉妬も欲望の感情も湧き立たせることはないのだが、問題は、心というものはちょっとでも隙を見せるとたちまち波立つような性質があるのだ。そしてサマタ瞑想法は持続性に欠けるのである。サマタ瞑想を止めてしまうと、また心は元の状態に戻ってしまう。
・日本の坐禅もサマタ瞑想のひとつだが、坐禅を行っているあいだは確かに怒りも欲望も少なく心は静かにしていられるのだが、一度坐禅を解いてしまうと心はまた元の状態にすぐもどってしまい、いろいろな感情を波立たせるのである。「慈悲の瞑想」にも同じことが言える。だから、お釈迦さまも「サマタ瞑想は一時的な効果しか期待できない」と話されている。
ほっておくと心の汚れは増すばかりですから、気づきをもって心の成長に努めることが必要とのことです。私は、やっと最近になりスマナサーラ長老の法話を聞く機会を得たことで、心の仕組みを知り、瞑想法を勉強し、実践しようとしているところです。縁がないとよき教えには巡り合わないものだと思っています。今回の資料は「上座仏教 悟りながら生きる」の第九章(人間、究極の心得)(234~265頁)から私なりに要約し抜粋したものです。興味を持ったら是非ともお読み下さい。