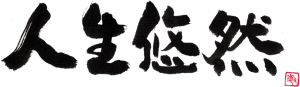1.仏教の原点をふり返ってみる
自分の心の中を覗いて見たことがありますか。頭の中では、常に考えが浮かんでは消え浮かんでは消えています。その内容も、あっちに飛び、こっちに飛んで捉えどころがありません。足を組み、背筋を伸ばし、姿勢を整えて、意識を呼吸に集中していても、すぐに全く別の思いや思考が割り込んでくる経験はあると思います。坐禅していると心の移ろいがこんなにも多くあることに気づくことができます。坐禅のような外部からの刺激がほとんどなくなるとよく分かりますが、日常生活のなかでは眼、耳、鼻、舌、身の感覚器官を通して、次々と多くの情報が脳内に流れ込んできます。それによって意識が生まれ、思考し、行動に移しているので、心がうつろっていることに気づきません。
私たちは自分の意志で思考して、その時々の状況に沿ってものごとを判断し、取捨選択していると思っています。しかし、残念ながら、意識が生じてアウトプットするときには、そのコンマ数秒前の無意識の時点で偏見や先入観による偏向がかかり、正しい見方ができなくなっているのです。生じた意識の中は、欲望や憎しみ、怒りなどの感情や自分勝手な思い込みなどで汚染されていることがあります。その結果、自分の思い通りには物事が進まず、そのギャップで苦しみが生まれます。
苦しみが生じる原因に気づき、その発生を抑え、心の平安を得る方法を仏教は説いています。「生きるとは何か」をテーマに仏教について長いこと考察してきましたが、この辺で仏教の原点をふり返ってみようと思います。
最近、仏教について分かりやすく解説されている本に出合いました。その本は、佐々木閑、大栗博司共著「真理の探究―仏教と宇宙物理学の対話」(幻冬舎新書、2016年)です。佐々木氏は花園大学教授で仏教学者ですが、京大の工学部と文学部を卒業しています。一方の大栗氏はカリフォルニア工科大学で最先端の超弦理論を研究している理論物理学者です。仏教については大栗氏の質問に佐々木氏が答える対話の部分と個別講義の部分があります。現代物理学については大栗氏により分かりやすい解説がなされています。釈尊の初期仏教と現代物理学で解明された宇宙の原理との接点も探っています。
人間を釈迦はどのように考えたのか、佐々木氏の見解に沿って仏教の原点を辿ってみます。読んでみて、私は佐々木氏の見方に同感し、納得しましたので少し長くなりますが、引用します。
生まれながらに偏見・先入観が刷り込まれている
・釈迦は、このように考えました。私たち人間は自分自身のことを、すぐれて理性ある生き物だと思いがちです。ところが人間の考えることには、最初から偏見や先入観などが刷り込まれている。それは私たちに責任があるわけでなく、生まれつき備わっている性質ですから、仕方のないことです。人間という生き物にとっては、それが生理的に自然なあり方なのです。
しかし、だからと言って、それを放っておくことはできません。その偏見や先入観が、私たち自身を苦しめる手かせ足かせになっているからです。人間の内部には、生まれながらにして自分の周りの世界を歪めた姿で見せる機構が備わっていて、そのために私たちは物事を正しく見ることができない。それが、苦しみを生みだす根本原因だと釈迦は言うのです。
ならば、どうすればいいのか。苦しみから逃れるには、自力で偏見のフィルターを取り去って、世界を正しく見なければいけません。それが、仏教の第一の目的です。まずは世の中を正しく見なければ、自分が生きていくべき方向性も見えてこないのです。・それでは、人間に生まれつきどんな偏見や先入観が刷り込まれているのか。いちばん根っこの部分にあるのは、「宇宙の真ん中に自分がいる」という思い込みです。自分が宇宙の中心にいて、その周りに世界が同心円状に広がっている、目に見えるのはそういう風景ですから、この発想はごく自然なものでしょう。そのために私たちは、自分のいる中心部分がいちばん濃密な世界で、遠くに離れるほどそれが薄まっていくようなイメージを抱きがちです。「世界は自分中心に動いている」という世界観です。しかし、この世界をよく見れば、そんなイメージは錯覚にすぎないことが分かります。
(真理の探究:16頁)
人間の心の在り方や性質を知っていれば、自分の言葉や行動は公平で、相手のことを考えていると思っていても、注意して心を覗くと、かなり自己中心的な判断を無意識にしていることに気づきます。仏教はこの偏見のフィルターがあることを気づかせて、取り除く方法を教えてくれます。日頃の生活のなかで、今日一日の出来事を静かに振り返ってみても、あの時の発言は本当に相手のことを思って言ったのか、自分の都合も考慮していると気づくことがあります。また、ある一つの問題を議論するにしても、参加者がそれぞれ持っている問題意識(先入観、経験など)も異なり、知識レベルも違います。司会者からするとなんで理解されないのか、説得することの難しさを感じると思います。それぞれが自分中心の世界に住んでいるのです。
宇宙の法則性を発見
・釈迦は、たいへん斬新的な宗教概念を作り上げました。絶対者のいない宗教世界です。例えばキリスト教やイスラム教の場合、この世には最初から神という絶対者が存在しており、神との契約によって、私たちの人生の幸不幸が決められると考えます。そして神の言葉を伝える伝達者として使わされたのが、キリストやムハンマドです。彼らは神の教えを私たちに伝えてはくれますが、彼ら自身が、その宗教の原理をつくったわけではない。これに対して仏教は、そういった神のような普遍的存在を想定しない宗教です。
ですから、釈迦は誰かの言葉を伝える伝達者ではありません。その人自身が、宇宙の真理の発見者です。それ以前から存在していた宇宙の法則性を見つけ出し、それを誰もが納得できる形で言語表現をした。その意味では、もちろん釈迦自身はそんな自覚はなかったでしょうが、科学者と非常に似た視点を持って生きた人物だったと思います。(同、78頁)
仏教を 学んで分かったことは、宗教では絶対なる神がこの世界を創造したとするなら、 仏教は宗教ではないということです。 あくまでも宇宙の真理を発見し、それを人々に説いてるのです。現代の科学的な知識で見ても論理的であり、矛盾がありません。以下に佐々木氏の解説が続きます。
・仏教では、世界をつくった創造主を想定しないので、この世界には「始まり」はありません。でも、法則性はあります。原因からは必ずそれに応じた結果が生じるというのが、その法則性です。科学の因果律と同じで、仏教の言葉では、「縁起」と言います。
縁起は自然界の法則ですから、釈迦が現れようが現れまいが関係なく、この世はそれに従って動きます。そこにたまたま現れた釈迦がその法則性に気づいて、私たちに教えてくれた。それが仏教という宗教の基本構造です。
すべてが原因と結果につながっていますから、同じものがそのまま存続することは絶対にありません。縁起でつながった全要素が、一瞬も止まることもなく変容し続けています。それが「諸行無常」という考え方です。
「諸行」とは存在であり、その存在と存在を結びつける関係性が「縁起」という法則です。法則それ自体は滅びようがない。その法則によって、諸行がどんどん変容していくのが「諸行無常」です。基本原理は三つ
・釈迦が考えた基本原理は、三つです。「諸行無常」「諸法無我」「一切皆苦」です。縁起の法則性に基づいて動くこの世のありさまを、三本の公式にまとめたものです。
すべての現象が縁起によって原因と結果でつながっている以上、ある存在が同じ形で永遠に続くことはありえません。これが「諸行無常」です。「諸法無我」とは世界の中心に自分=「我」が存在すると考えるのは錯覚だということ。諸法の「法」は仏・法・僧の「法」(仏陀の教え)とは別物で、「この世の実存在」という意味です。
この諸行無常と諸法無我の二つの真理を知らずにいると、生きること自体が苦になるでしょう。それを「一切皆苦」と言います。この三つが、仏教の旗印。「仏教の世界観はこうだ」と主張するわけです。 (同、95頁)悟りへの道筋
・この三つの旗印に加えて、仏教には「四諦」という言葉があります。「苦」「集」「滅」「道」の四つで、こちらは仏教が私たちにとってどういった有益性をもつかを示したもの。「諦」は「諦める」ことでなく、「真理」という意味です。インド語では「サティア」。四諦とは「四つの真理」ということです。このうち「苦」は説明不要でしょう。一切皆苦の「苦」。「この世の本質は苦しみだ」という真理です。次の「集」は、「原因」を意味するインド語が原義ですので、漢字はあまり気にしないでください。「苦」の原因のことを「集」と呼びます。
我々の苦は、老・病・死という、避けがたい災厄から発生してくるのですが、その老、病、死を苦の原因だと考えてはいけません。仏教の目的は苦を消すことなので、老、病、死の苦が原因だとすると、老、病、死を消すしかなくなってしまいます。そんなことはできるわけがありません。老、病、死は絶対に避けられない現象ですから、それを苦の原因、つまり「集」とは考えないのです。
では何が「集」なのか、仏教では、老、病、死を「苦」に変容してアウトプットする心的システムこそが、苦しみの原因と考えます。それは、私たちの心のなかにある煩悩にほかなりません。「無明」を中心とする間違ったものの見方、考え方が「集」なのです。
三番目の「滅」は、その集が消えるのか否かという問いに対する答えです。自分の努力によって苦しみの原因を消すことができるという事実を意味しています。
そして四番目の「道」は、「滅」を実現するための方法。釈迦が教えるトレーニング方法を信じて実践しなさい、というのが「道」の意味です。
あらためて「苦・集・滅・道」の流れをまとめると、「この世は苦しいけど、その原因を消す方法は間違いなくあるのだから、それを信じて正しい道を進んでいきましょう」ということになります。
(同、99-100頁)宗教と科学の共通性と違い
・仏教は、一般的な宗教と違って、外的な力による救済を一切認めないところです。「神に救ってもらう」と言った思い込みをまったく含みません。その一方で、「生きることは絶対的な苦だ」という世界観の上に立つ。生きることは本質的にすべて苦しみであって、楽しみはその上に浮かぶ儚い泡のようなもの。その生きる辛さを自分の智慧で解消しろと釈尊は言うわけです。自分の心の中に苦しみを生みだすシステムがあるから、それを自分の力で変えなければいけない。釈尊はそのための方法まで教えてくれました。それは「よく考えろ」ということです。それは別な言い方をすれば「世の中の本当のあり方を見る」ことなので、そこに科学との共通性を感じるのです。もちろん、科学は私たちの苦しみを消すために存在するわけではありません。
・科学の世界には、まず「この世の正しいあり方やその法則性を知りたい」という思いがあり、科学者が次々と新しい世界観を作り上げていきます。ところが、多くの人々は、そういう科学の驚異的な発展とは無縁に、従来の常識に従った暮らしをしています。科学は世界の真実を語っているのに、私たちはその科学を自分のこととして親身に受け入れていないという、不思議な現象があるわけです。
・一方の宗教は、その逆だと思います。自分のこととして受け入れなければいけない現実が先にある。「死」であれ「病」であれ、いま持っているものを失わなければならないという現実です。これは、のほほんと暮らしている日常世界に突如として現れる世界の崩壊なのです。その崩壊現象から自分の精神を守るために、新しい世界観を求める。それが宗教です。
その新しい世界観の中でいちばん典型的なのは、「死なない」という世界観でしょう。宗教が与える死後の世界が本当にあるかどうかは、科学的問題ではない。自分の世界観が崩壊するときに支えてくれるものであれば、その世界観には価値があります、価値のある世界観は正しいかどうかが問題ですが、宗教のつくる世界観は、客観的事実であるかどうかよりも、自分の精神の支えになるかどうかが優先されるのです。生きる意味を見つける
・宗教の本質は、本源的な苦しみを軽減してくれるような世界観を提供するところにあります。「死ぬのはいやだ」という、人の本能的苦悩に対処するため、「肉体は死んでも魂はしなない。その死なない魂には永遠の安楽が約束されている」と説くキリスト教やイスラム教が大いに安心のもとになったのは当然です。これらの宗教が説く世界観を疑いようのない事実として受け入れることのできる人にとっては、それはこの世で最高の救済となります。「死んだあとに最高の幸福が待っている」と言うのですから、これ以上の喜びはありません。もし私が、これらの宗教が登場した時代に生まれていたら、一も二もなく、その世界に身を委ねたでしょう。
しかし、現在の科学的世界観の世の中で生きる私たちは、そういった自分の死後にとって都合よく組み立てられた死生観の実在性を信じることができないという点にあります。そこで、釈迦の説く「誰も生きる意味を与えてくれない世の中で、絶望せずに生きるためには、自分の力で生きる意味を見つけていかねばならない」という教えが意味を持ってきます。
ですから、「自分の力で生きる意味を見つけていくなんていう困難な道は、とても進めない。私はまわりの誰かが説き示してくれる救済の道を信じて、それについていくしかない」と考える人にとっては、釈迦の仏教は影響力を持ちません。実際、そう考えて、釈迦の仏教から脱却を図ったのが大乗仏教です。「世の中を正しく見つめる」姿勢が釈迦の仏教
・釈迦の仏教には、「正しくなくてもおもしろければいい」という人を無理に矯正して転向させようという意思がありません。「たとえそれが自分の意に沿わないことであっても、世の中を正しく見ることが苦しみを消す唯一の道だ」と確信した人にしか、仏教は意味を持たないからです。ですから、そのままほっておくしかないのです。
ただし、ここが大切なのですが、そぅいった他者への絶対信仰をよりどころにする生き方や、あるいは正しさよりおもしろさを重視する生き方は、物事の正しさ、つまり現実の本当のあり方に特定のフィルターをかけて、現実と食い違った視点で物事を見ながら生きることになります。ここで言う現実の本当のあり方とは、長い時間をかけて人類が到達した、意識の機能を最大限に発揮して得られる世界観、すなわち科学的世界観に基づくこの世のあり方であって、それは釈迦が想定した世界と一致します。なぜ日本は大乗仏教が主流なのか
・仏教がインドから中国に伝わるには、紀元前後にシルクロードが開通するのを待たなければなりませんでした。スリランカをはじめとする南方へは比較的早い段階で海伝いに仏教は広まりましたが、北方へは陸路でないと出られません。そのあいだにインドでは、従来の釈迦の仏教とは違う大乗仏教が新たに誕生しました。釈迦のつくったオリジナル仏教がシルクロードというゲートが開くのを待っていたら、後ろから大乗仏教がやってきたわけです。そのため、ようやくゲートが開いたときには、オリジナル仏教と大乗仏教が肩を並べて一緒に中国に入ることになりました。
当然、中国の人々は困惑します。別々の顔を持つ宗教がどちらも仏教を名乗って入ってきたのですから、意味がよくわかりません。したがって中国では、仏教の中身をめぐって混乱状態が数百年間も続きました。 (同、106頁)
東方学院で加藤講師から「法顕伝」の講義を受けました。法顕は西暦399年にインドに向けて長安を出発しています。律蔵の欠けているところを補うために、戒律を尋ね求めることを目的にしたとの記述があります。途中に立ち寄った西域の国々は、大乗仏教が盛んな国と小乗仏教が盛んな国が入り混じっている状況が書き留められています。しかし、法顕は小乗仏教については特に興味を示していません。四世紀か五世紀にかけてどちらの仏教も盛んであったのに、中国では五世紀ころには中身をめぐる混乱状態が終息していたのでしょうか。佐々木氏の解説を続けます。
・数百年かけてようやく整理がついたわけですが、それも決して正しいものではありません。釈迦オリジナルとされる古いお経も、大乗仏教の成立後につくられた新しいお経も、どちらもひとまとめに「お経」として入ってきたので、中国側にはその時間的な奥行きが分からなかったのでしょう。お経と名のつくものはどれもこれもすべて釈迦の教えとして受け入れてしまいました。
その結果、同じ釈迦が説いたとされるお経の中身が、ものによっては全然違うということになります。そこで、「釈迦は相手によって入門編と本格的な教えを使い分けていたのだろう」とか、「釈迦の若いときの言葉はあまり深いものではなかったが、亡くなる間際に本当の言いたいことを言ったに違いない」といった解釈によって、中身の違いを説明するようになりました。つまり、釈迦というひとりの人物の生涯の上にあらゆるお教を位置づけた。これが中国における仏教学の本質です。
そうなると当然、人によってどのお経を大事にするかが違ってきます。「般若経が釈迦の教えの本質だ」と考える人もいれば、「いや法華経こそが仏教の中心である」と考える人もいる。それぞれの個性や価値観によって選ぶお教が異なります。これが、仏教にさまざまな宗派が生まれる起源になりました。
ここで重要なのは、いろいろなお教が選ばれる中で、最も成立の古いお教である阿含経(ニカーヤ)を選ぶ宗派が中国になかったことです。選ばれたのは、いま例にあげた般若経や法華経などの大乗仏教のお教ばかりでした。なぜ、そうなったのかと言えば、大乗仏教の方が神秘性が高くて、宗教として一般の人に人気があったからです。
釈迦の仏教は努力による自己変革を求めますが、大乗仏教はそうではありません。「不思議なパワーによってみんなが救われる」という宗教です。どちらが大衆の心にインパクトを与えるかは、いうまでもありません。
そして日本は、その中国から仏教を受け入れました。だから釈迦本来の仏教を伝える阿含経を根本経典とする宗派が何処にもありません。こうして日本は、大乗仏教一色の仏教国になったわけです。 (同、107-108頁)
当然、日本の仏教も、どのお経に感銘を受けたかで宗派ができました。法華経に自分の生き方を投影したのが日蓮で、その教え基にして日蓮宗が成立します。無量寿経に感応して南無阿弥陀仏と唱えるようになったのが法然の浄土教です。親鸞は法然に帰依して教えを広めますが、後には浄土真宗になります。その他、概要を「生きるとは何か」(29)(2013年9月)で述べました。
最近では、日本の大乗仏教の教えでは満足できない人たちが、釈迦本来の仏教を伝えるテーラワーダ仏教に関心を高めています。スリランカから来日したスマナサーラ長老の説法をたくさんの人たちが傾聴しています。分かりやすく書かれた書籍も多く出版されていますので、読んで見るとそこには真理がストレートに語たられています。私は最初にスマナサーラ長老の説法を聞いたときに、シンプルで直接心に響く言葉に感動を覚えました。釈迦の言葉で教えを伝えているテーラワーダ仏教にたどり着いたのは当然の帰結のような思いです。
テーラワーダ仏教仏教とはどのようなものなのか簡単に説明されています。
スリランカに伝わった初期仏教(上座仏教)
・釈迦はインドの北部を中心にして活動していました。徒歩で布教していたので、釈迦自身が生涯を通してまわることができたのは、かなり狭い地域に限定されます。釈迦の死後、仏教はそこから次第にまわりの地域へと広がっていきます。
その仏教が海を渡ってスリランカに伝わったのは、紀元前三世紀頃と言われています。釈迦は紀元前五世紀頃の人ですから、比較的早い段階で仏教を受け入れたのがスリランカでした。そのときスリランカに伝えられた仏教は、インドの地方方言のひとつであるパーリ語という言語で説かれたものでした。
この時代はまだ大乗仏教が生まれていませんでしたので、スリランカには釈迦のつくったオリジナルの仏教が入りました。しかも彼らはそれを自分たちスリランカの言葉に翻訳せず、外国語であるパーリ語そのままの形で受け入れて覚えました。そのため現在でも、スリランカでお坊さんになる人たちは、スリランカ語とは別に、パーリ語も学ぶことになります。
そのスリランカの仏教がのちに東南アジアに伝わったため、タイやミャンマーなど東南アジアの国々でも、お坊さんはパーリ語でお教を唱えます。ですから、スリランカとタイのお坊さんは、母国語が違うのに、会えばパーリ語で会話ができるのです。このときスリランカに伝わった経典を一般に「南伝パーリ聖典」と言い、大きく「律蔵」「経蔵」「論蔵」の三つに分類されています。
仏教聖典が初めて文字化されたのは、南方仏教国の歴史書によれば、紀元前一世紀とされています。 (同、101頁)
スマラサーナ長老のお経も当然パーリ語で唱えています。法話会に参加している多くの日本人もパーリ語で唱和しています。慣れるとリズミカルで心地よく聞こえてきます 。
ここで観点を変え、対談の相手である大栗氏の宇宙的な視点から見た世界の見方を、少しですが参考として記載します。
すべての根本はエネルギ―問題
・大栗:私は経済成長のカギは、根本的にすべてエネルギ―問題に帰着すると考えています。人間の社会活動の基本は、ものをつくり、情報を蓄え伝達することで秩序を生みたしていくことです。商品であれ、美術や音楽であれ、建築物であれ、人間は自然界にないものを次々とつくってきました。これは一見すると、熱力学の第二法則と真っ向から矛盾します。
・佐々木:エントロピー増大の法則ですね。
・大栗:はい。これは簡単に言うと「覆水盆に返らず」と言う法則です。ガラスのコップを床に落とすとバラバラに砕けますが、バラバラの破片が元に戻ってコップになることはありません。コップという秩序ある状態はエントロピーが低く、バラバラの状態はエントロピーが高いわけです。自然界では、放っておくとエントロピーが増大するので、秩序あるものはいずれ壊れてしまう。まさに「諸行無常」が自然界の摂理なのです。
ところが人間は次々と自然界に新たな秩序を生みだしています。そもそも単細胞だった生物が多細胞の複雑な構造を持つようになったこと自体が、エントロピー増大に反しているように見えます。それが可能になったのは、お天道様のおかげです。太陽から届くエネルギーがなければ、こんなことはできません。地球は太陽のエネルギーを受けて、最終的にそれを宇宙に拡散することでエントロピーを増大させているので、少しぐらい人間がエントロピーを減らしてもつじつまが合う。それによって地球上に文明が生まれたわけですから、文明をいかに持続・発展させるかは基本的にエネルギ―問題なのです。
ともかく熱力学の第二法則は自然界の基本法則なので、それと真っ向から対立する人間の文明を維持するには、太陽のエネルギーを効率的にとらえて利用する必要があります。それができなければ、いずれ中世や近世あたりの経済規模に戻らざるを得ないでしょう。 (同183頁)
私たち生命がこの地球上に存在して、文明を築き、75億以上の人間が生存できるのも、太陽エネルギーの恩恵があればこそ生きていけるのです。化石燃料は植物が何十億年かけて太陽エネルギーを濃縮したものです。それを人間が掘り起こして燃やすことでエントロピーを増大させています。その一部を使うことで文明社会を築いてきたわけです。最近では、「物質的豊かさでは幸福になれない」などと言われていますが、それは経済的余裕があっての話で人間のエゴです。人間の性格は、強い生存欲と偏見に満ちたものです。
東日本大震災の時に、普通の日常生活が奪われ、平穏な生活の有り難さや素晴らしさに気づかされましたが、しばらくすると仮設住宅の平穏な生活が苦しみに変わっています。人間は常に刺激を求め、欲望を満たすために走りまわります。ほどほどで満足できない性格なのです。
2.上座仏教の長老の言葉
人の心は本来どのようなものなのか、スマナサーラ長老の言葉をスマナサーラ著「上座仏教 悟りながら生きる」(大法輪閣)から拾ってみます。
・人間の心は本来、穢れていて悪いものなのだ。清らかでもないし、美しくもない。自分勝手で、わがままで、自己愛だけに守られて生きているのが真実の心の姿なのである。決して、きれいごとの世界ではないのである。
・心はただただ、今この瞬間の刺激を求めようとする。いいことであろうと悪いことであろうと、そんなことにはお構いなしに、すぐに目先の現象を追いかけていく。自分にとってそれが良い結果になるか、悪い結果になるかという判断すらも心にはできない。善悪の区別もつかないところは、幼児とまったく同じである。子供は、いまを楽しく遊んでいればそれで十分満足で、そのことが後々自分にとってマイナスになるということなど考えない。心も、まったく同様である。
この状態を、仏教では「無明」と言う。無明とは、明かりがない状態、心が冴えていない状態、智慧のない状態を言うのである。無明とは、人間が欲望という名の催眠術にかかっているときの状態であり、そのために目の前の真理を観ることができない。心は、まさにこの「無明」そのものである。心は、放っておけばどんどんこの無明に誘われて、悪い方向に向かってしまう。
最近の新聞やテレビを賑わしている話題を見ると、人の心のあり方が透けて見えてきます。加計学園の認可や森友学園の用地買収問題に対する国会での安倍首相や高級官僚たちの答弁、さらには日本大学のアメリカンフットボール部の監督やコーチの責任逃れの発言など、人の心は如何なるものかが分かります。彼らは世間的に最も高い地位にいて指導する立場であり、本来ならば尊敬されるべき人たちです。権威があり、名誉があり、地位が高いとなると強い執着心があり、失うことへの恐怖心も大きくなることでしょう。自分勝手で、わがままで、自己愛だけに守られて生きている姿は、欲望という名の催眠術にかかった状態のようです。釈迦は2600年前に見抜いています。
今回は、250頁もある著書から私の筋書きに沿って、つまみ食いしたようなものです。また共著者の大栗氏の理論物理学からの視点も紙面の都合で省いていますから、興味を持たれた方は原本を手に取って読まれることをお勧めします。